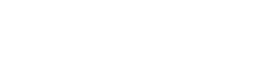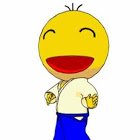10/30 柳生新陰流の稽古
柳生新陰流(以後、「柳生流」とします) 柳生天狗堂の池之側 浩 師の下での月1回の剣術稽古
合気道の組太刀を剣術として破綻がないように再構成していただき、八幡男山道場の稽古で用いることができる形にしてみました。差し当たりこの日は一之太刀と二之太刀を再構成しました。
次に柳生流でもっとも基本となる「前後斬り」と「廻剣」の素振りの点検をしていただき、初伝の形である「三学円之太刀」の内、「一刀両断」と「斬釘截鐵」を御指南いただきました。
なぜ柳生新陰流なのか
合氣道では「合氣道は剣の理合いである」とする旨が植芝盛平翁の言葉として伝わっています。では、その「剣の理合」とは何なのかは、よく知りませんでした。合氣道家の中にも、杖術や剣術、居合を併修されている方も少なくなく、やはり「剣の理合」を探求されているのだと思います。
翁先生は三十優余流の武術を学ばれたと言われていますので、その中の剣術の流儀も一つではないと思われます。書物などで翁先生の修行歴を辿ると、武田惣角師から「進履橋」という柳生流の伝書を授かったという伝えがあります。また、翁先生は昭和初期に新宿若松町(現在の合気会本部の所在地)にあった、柳生巌周(柳生新陰流宗家19世)の高弟である下條小三郎師が主宰する檪山館にて柳生流との交換教授をされたと伝えられています。檪山館と合気道本部(当時は皇武館)の所在地は、かなり近いところあったようで少なからぬご縁を感じます。
術理においても、合気道と通ずるところが見られます。柳生流は「輪の太刀」に代表されるように「転(まろばし)」の術理が特徴的です。これは合気道の円転の理と共通性があり、輪の太刀からの斬りこみは入身投を彷彿とさせます。柳生流の柄の持ち方は「龍之口」と呼ばれる手の形を示しますが、この手の形は合気道の一教、二教、三教といった極め技にそのまま用いることができます。
理念においても、柳生流は殺生を好まない「活人剣(かつにんけん))を説いており、剣術のみならず治世の兵法として徳川将軍家に重用されました。これは争わず和合を目指す合気道の精神との親和性を覚えます。
冒頭に述べた通り、翁先生は多くの武術に通じられていたので、「合気道の剣の理合は柳生流だ」とまで断言はできませんが、より近いエッセンスはあるだろうと見立てています。少なくとも剣術を何も知らないまま「剣の理合」語るのはよろしくありませんので、八幡男山道場の剣術の指針として柳生流を採用しています。