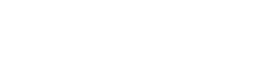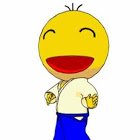11/19 京大合気道部での出稽古
【ご指導】大阪合気会指導部 師範 門川勉 先生
道場に訪れたとき、昇級・昇段審査の最中でした。
同部の昇級・昇段審査のスタイルは、門川師範の指定する入り(正面打・横面打 etc)で有段者が次々と受験者に掛かっていくというものでした。有段者も人数が多いものですから審査を受ける側も20人くらい取らなければなりません。これ、有段の部員が多いからできる審査方法ですよね。ウチの道場ではようしません。掛りの取りを終えると次は多人数掛(4人)に移ります。昇級試験でも昇段試験でも多人数掛けの審査をするのですね。白帯の昇級試験では、先輩たちも技にかかってくれますが、昇段試験はそうした忖度がない模様で正面打や横面打がボカボカ当たってます。
あまり多人数掛けをやったことがないので、偉そうなことは言えませんが昇級試験でも昇段試験でも、投げようという意識が強すぎるのではないかと感じました。投げると居つきが起こりやすくなります。合氣道の多人数掛けでは取りが投げを打つときに他の受けは攻撃をしないという暗黙の決まりがあるようですが、それでも投げを打ってしまうと次の攻撃に対処できず詰んでしまいます。囲まれた場合は、先ずは囲みの外に抜けることが肝要ではないかと思います。その際に用いるのが入身や転換です。例えば4人の内、誰か一人に目標を定めて入身をすると、その相手の背後に入り少しの間は囲みの外に出られます。その入身をしたまま投げを打たず、相手を盾にするように他の相手に向かわせると二人の動きを封じることができます。そうしている間に次の相手に向かうという要領でしょうか。
昇段級審査の後、一つだけ技の稽古をする時間があり、参加しました。
<1>肩取正面打入身投
逆半身で取りに肩を取られた状態から正面打をされ、それを取られている肩の方の腕で合わせるのですが、門川師範は合わせた後の腕の動かし方が特徴的です。受け止めるでもなく、上方にせり上げるでもなく体を開きながら肘を折るような形で受け流して、そこから入身投に入ってゆかれます。見慣れない技に接した時には、剣術でどういう体捌きになるのかといいう視点で考えるのですが、いま身につけている剣術の動きの中では、これだという形が見出せないので、まだまだ研究が必要なようです。