11/8八幡男山道場の稽古
子どもの部
緑帯2,黄帯1、初心4、助教1
この日の稽古も、12/13の枚方無心館道場の演武会に向けた基本技の稽古。
演武技予定としては
<初心・初級>
正面打一教(表)、正面打入身投、天地投
<青帯以上>
上記に加え、正面打一教(裏)、正面打回転投、横面打四方投、逆半身片手取隅落し
夏に入門した数名の道場生の受け身も技も形になってきました。やはり繰り返し稽古することは大切です。
大人の部
初段3人、1級1人、初心1人
大人の部も12/13の枚方無心館道場の演武会に向けた技を稽古。
なお、演武予定技は、正面打一教、中断突小手返、中断突入身投、後取四方投、逆半身片手取二教
【稽古技】
<中段突小手返>
逆半身から入身転換するが、受けの突きの手首を掴もうとしがちだが、実戦があるならば、おそらくそれはできないだろうし、受けの手首を掴むことに執着すると自身の転換動作が崩れやすい。自身の手が受けの前腕のどこかに触れられれば足りる。自身の手を濡れタオルのようにイメージし、相手の前腕のどこかにペタリと引っかける心持ち。その接触点から転換動作で崩したい。崩すことができれば受けに居つきが生じるので、そのタイミングで小手を持ち返しに入る。このとき、腕を左右に振ることで小手を返すのではなく、表・裏への足運びと体幹と腕を一致させる中で技となる。腕の動きは上下だけで足りる。
演武向けの跳び受け身のための動作ポイントとしては、取りはあまり急いで投げようとせず、転換後に受けとしっかり向き合うまで待つことが肝要。また、転換後に受けが止まってしまうと上手く跳び受け身に入っていけないので、裏技なら取りに殴りかかるように向かい、表技なら取りを引き込むようにすると良い。また、取りも投げも思い切りが大事で、変な躊躇をされると跳びにくいもので、むしろ衝撃の大きい受けになりやすい。また、跳び受け身をする投げを打った後は、投げっぱなしにするのではなく、受けの背中が接地する少し前に僅かに引き上げると親切でしょう。引くといっても受けの腕を伸ばすように強く引くと肘や上腕を脱臼しかねない。小手返しの腕の動きは中段から下段への振り下ろしであるが、取りの小手の軌道としては数字の「6」の字を書く要領になる。「6」の下の円は小さめに描くといいでしょう。別の表現をすると、フィナボッチ曲線(下図ChatGPTで生成)に近い軌道になるのではないでしょうか。
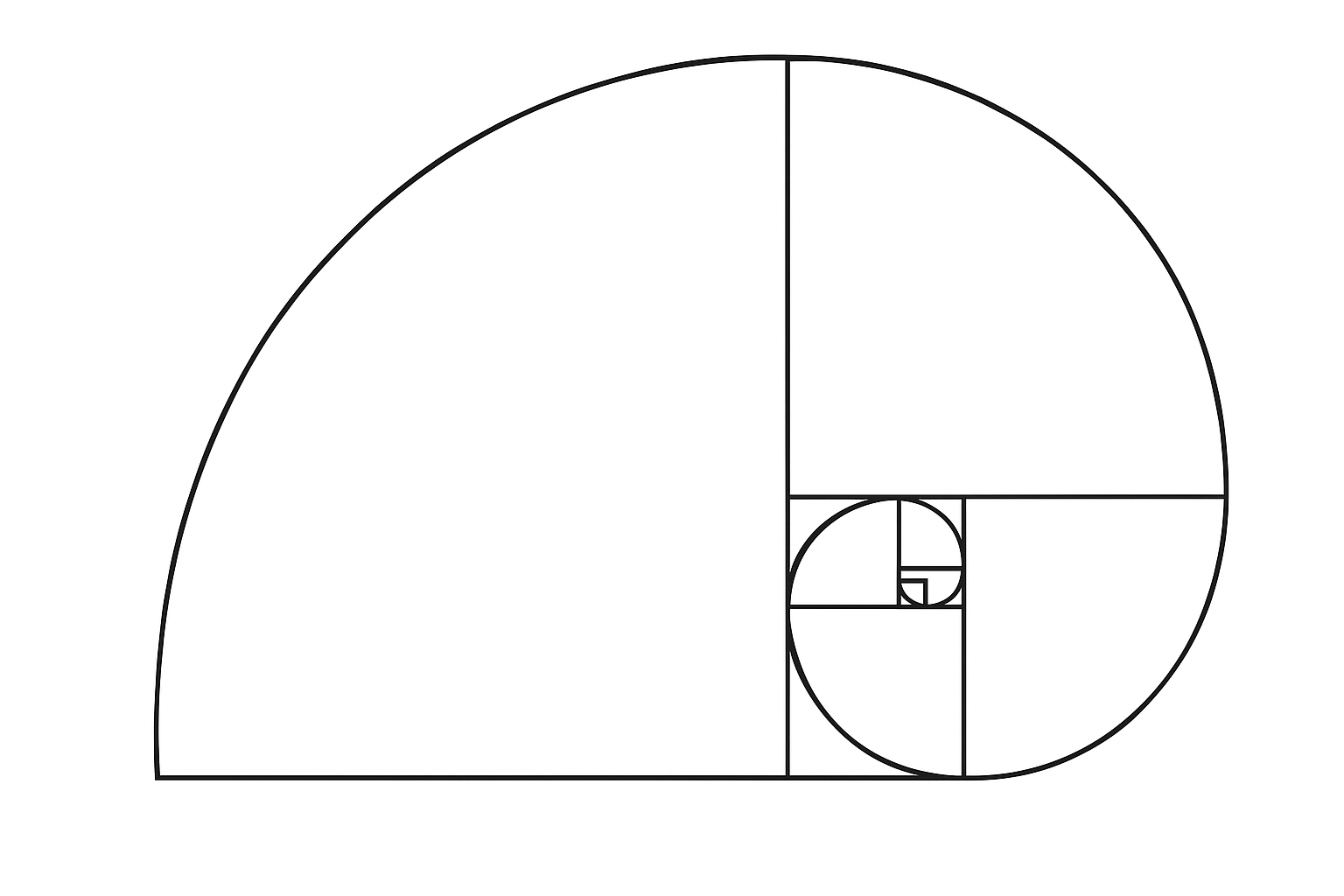
<逆半身片手取二教>
前週も同じ技を稽古しているので、重複するところは割愛。二教でありがちなのは、手や腕で捏ねるように受けの腕をS字にもっていこうとする動きがみられるが、これは避けたい。取りの腕や手はできるだけ自身の人中路を外さず、足運びによる体幹の操作によりS字にもっていきたい。極めに入るとき、これもまた手や腕を押し下げるようにしがちだが、受けの手首が痛くなるだけで崩れにくい。受けの腕をS字にすることで受けの腕と体幹は纏絲がかかり繋がるので、取りの体幹の重心落下を受けに伝えることで崩したい。この際、膝を弛めるだけでは前方への運動しかおこらないし、膝が前に出すぎて痛める原因にもなりかねない。脛骨は床と垂直な状態を保ち、床からの反作用を使えるようにしたい。膝を弛めると同時に股関節を畳むような脱力と合わせることで、体幹の重さが垂直方向に働かせることができ、その反作用も利用しやすくなる。
また、脚の動きとしては大腿骨頭を内旋させる動きとなるが、これは左右いずれかの脚を軸にしてもう片方の脚を内旋させるのではなく、両足を内旋させることで重心が乗っていない「虚」の方の脚が結果として動くことになる。体軸はあくまで人中路にあり「重心=体軸」ではない。膝行も基本的に同じ動作であろうかと思う。
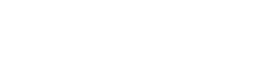
-300x300.jpg)